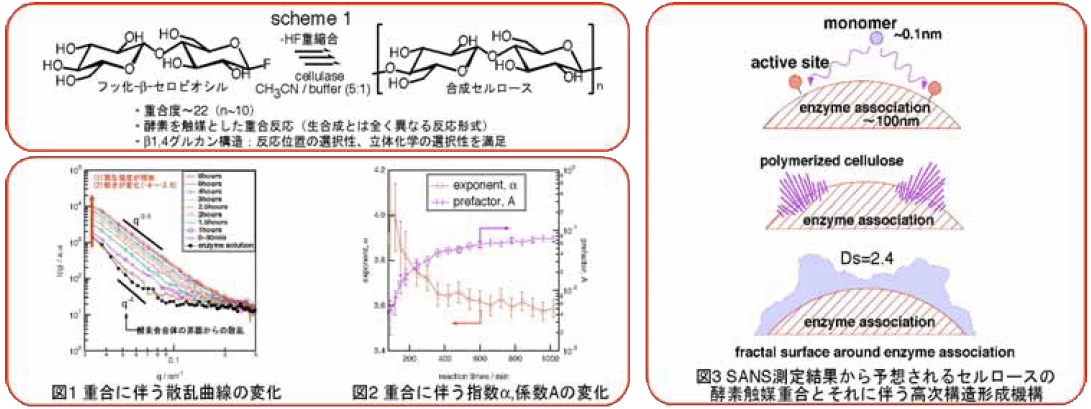【中性子小角散乱が観るセルロースの酵素触媒重合と組織形成】

【中性子小角散乱が観るセルロースの酵素触媒重合と組織形成】
●先端基礎研究センター ソフトマター中性子散乱研究Gr 田中 宏和 ・ 小泉 智 ・ 橋本 竹治
セルロースは地球上に最も多く存在する高分子であり、我々の日々の生活に不可欠な素材である。通常セルロースは植物や微生物による天然合成によって生成されている。
長い高分子研究の歴史の中でセルロースの人工合成は重要な課題とされながら、成功には至らなかった。しかし1991年小林らは、
本来セルロースの分解酵素であるセルラーゼを利用した酵素触媒重合により初めて人工合成に成功した。ただし得られる分子の長さは、重合度20程度と極めて短い。
酵素触媒は特定の基質だけに作用し、かつ特定の反応のみ促進するという極めて優れた選択性を兼ね備えている。このような酵素の利点を最大限活用することによって、
従来合成が困難であった複雑な構造の化学物質の合成が可能となるのである。
酵素触媒による化学反応では、基質が酵素の活性部位を認識する過程が重要である。セルロースの人工合成の場合は、
クレフトと呼ばれるタンパク質分子の溝が活性部位にあたる。また活性部位からはセルロースが排出されその近傍で結晶化する。
つまり酵素活性部位や反応生成物の構造が反応性を大きく左右する可能性がある。
ソフトマター中性子散乱研究グループでは酵素触媒重合によるセルロースの人工合成を中性子小角散乱(以下SANS)でその場観察することを試みた。その結果、
ナノメートルからマイクロメートルに及ぶ広い空間スケールで人工合成過程に生成されたセルロースが酵素表面で形成する自己組織化構造を明らかにすることができた。
中性子散乱は本系のような「化学反応と構造形成が密接に関連する系」における構造観察手段として非常に優れている。
実験の詳細は以下の通りである。反応基質としてフッ化-β-セロビオシルをアセトニトリル-酢酸緩衝溶液(pH=5.0)(5/1, v/v)に溶かし、
そこに酵素であるセルラーゼを重合触媒として加える (Scheme 1)。これを厚さ2mmのクォーツセルに入れ、30℃、常圧下、中性子散乱の測定を行った。
用いた装置はJRR-3に設置された中性子小角散乱装置SANS-JおよびPNOである。SANS測定結果を図1に示す。図1より時間とともに散乱強度I(q)が単調に増加している。
これは生成したセルロースが触媒表面で結晶化した結果生じた自己組織化構造の時間変化を示す。次に散乱データの詳細をみてみよう。
時間によらず散乱強度I(q)と波数qの両対数プロットが直線状であることが分かる。この傾きはさらに2桁小さな波数まで続いている。
ここで直線の傾きを-a、係数A(比界面積)、定数B(非干渉性散乱)として、散乱強度I(q)を
I(q) = Aq-a + B・・・(1)
と近似してみる。(1)式を用いて各重合時間における散乱曲線をフィッティングした。その結果得られたa及びAの時間変化を図2に示す。
図2よりaは時間とともに減少しAは時間とともに増加することが分かる。またいずれの値も重合開始から約200分の間に急激に変化し、以降ほぼ一定値に近づいていることが分かる。
これはモノマー消費量の時間変化とも一致している。一般的に、I(q)とqの間に(1)式のようなベキ乗則が成り立つとき、構造が自己相似性(フラクタル性)をもつことが示唆される。
今の場合は界面構造にフラクタル性がある。ここで界面フラクタル次元をDsとすると、aは
a = 6 - Ds (2 < Ds < 3)
と表される。つまりセルロースが酵素表面で形成する結晶構造の界面(表面)は重合が進むにつれて次元Ds=2.4へと変化することが分かる。 この状況を模式的に示したのが図3である。重合前には酵素表面は滑らか(次元Ds=2、これはポロッド則と一致する)であったが、 セルロースの生成に従って粗い界面(2 < Ds < 3)へと変化する様子が明らかとなった。つまり、まず酵素会合体の活性部位がモノマーを認識することで重合が開始する。 生成されたセルロースは酵素から遊離することなくその表面近傍に留まって、新たに生成されるセルロースとともに次元Ds=2.4をもった結晶構造を酵素表面の活性部位周辺に形成する。 植物や微生物による天然合成で生成されるセルロースは重合度数千から数万であり人工合成とは比較にならないほど大きい。 この差の要因として上述した酵素表面でのセルロースの結晶化が挙げられる。つまり結晶化および結晶構造が重合反応に影響を与えているのではないか。 この点を中性子小角散乱によって明らかにし、それが重合度の制御に繋がれば素晴らしいと考え、更なる実験を企画している。