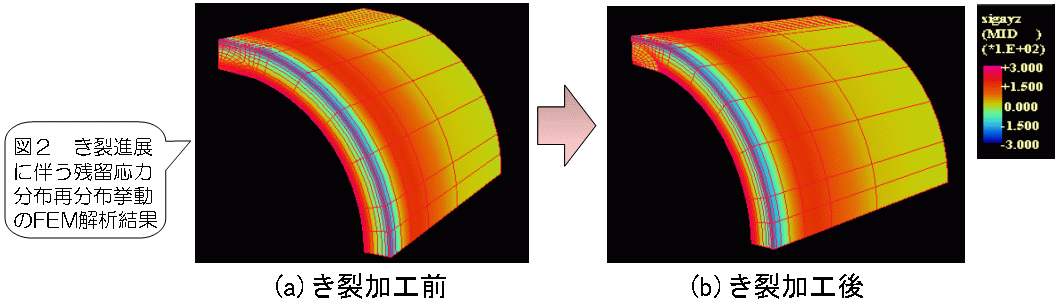【材料内部の残留応力測定による実構造物健全性評価技術の開発】

【材料内部の残留応力測定による実構造物健全性評価技術の開発】
●(株)日立製作所 日立研究所 エネルギー材料研究部 大城戸 忍
X線と比較して侵入深さが極めて大きい中性子の特性を利用した研究として、構造物の残留応力測定や、材料劣化評価がある。特に残留応力測定に関しては、材料内部の三次元的な応力マッピングが可能であることから、構造物の設計支援技術として活用されている。この技術は製品に直結した研究が多く、中性子の産業利用の代表例である。測定対象としては、航空機部品、ガスタービン翼、熱交換チューブ、原子炉材料、配管、熱遮蔽コーティング膜、自動車用エンジンなど重電機器や産業機器、自動車に関わるものが主流であるが、最近ではエレクトロニクス産業でも利用され始めている。
このような背景を受け、欧州ではVAMAS (The Versailles Project on Advanced Materials and Standards) において中性子回折による応力測定法の標準化を目的とした分科会TWA-20 "Measurement of Residual Stress"が組織され中性子回折法による残留応力測定標準を作成した。日本においても、日本材料学会のX線材料強度部門委員会において中性子応力測定標準を作成中である。
原子炉を用いた場合の中性子回折法による残留応力測定では、原子炉で発生した中性子線をモノクロメータを通して単色化し、検出器を2θ走査して回折ピークを求める。残留応力や負荷応力により材料の結晶面間隔が変化すると回折角度が変化する。ここで応力が無い状態における結晶面間隔をd0、その時の回折角をθ0とすると、結晶面間隔の変化量Δdと回折角の変化Δθとの関係は Δd/d0=−cot θ0・Δθ であり、ひずみ(Δd/d0)はΔθに比例する。主応力方向が明らかな場合には、直交する3方向のひずみを測定し、Hookeの式から応力を求める。
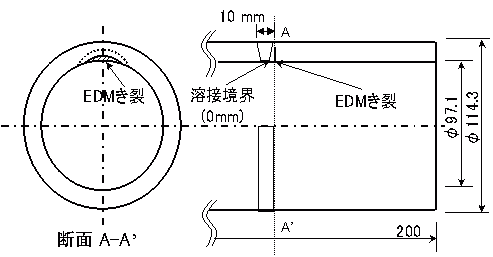
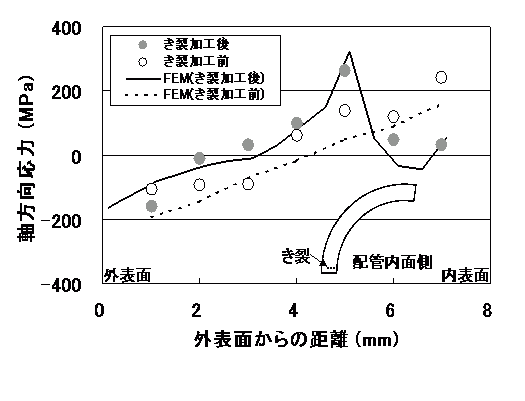
図1 突き合わせ溶接配管の溶接部近傍におけるき裂進展に伴う残留応力分布挙動の測定結果
構造物の残留応力を測定・評価した例として、突合せ溶接された100A配管を対象にした結果について以下に紹介する。溶接部には熱履歴に起因した高い残留応力が発生する場合があり、疲労や応力腐食割れの一因となっている。残留応力場でき裂が進展すると、当該部の残留応力が解放されるため、残留応力が再分布し、き裂進展挙動が変化する。図1は、ステンレス製配管の突合せ溶接部におけるき裂進展に伴う残留応力分布の再分布挙動を中性子回折法で評価した結果である。図中には有限要素解析(FEM)による計算結果も併せて示す。FEMの計算結果は中性子回折法の測定結果と良く一致している。中性子回折法の課題は、肉厚の大きい構造材料を対象とした場合、多くの測定時間を必要とすることである。図2には、中性子回折で実測したき裂長さよりさらにき裂が進展した場合の残留応力分布挙動をFEM解析で評価した結果を示す。き裂進展させた条件では、き裂最深部の残留応力は圧縮であり、表面き裂側では溶接初期の引張り残留応力がそのまま残留していることがFEM解析の結果から判断できる。このように有限要素法による計算と中性子回折法による実測は互いに補完関係であることが望ましい。このような結果は、構造物の設計やき裂進展挙動の予測・評価を可能にする。
今後は本技術の高精度化を図り、複雑な残留応力場への本手法の適用することを計画している。最後に本研究の遂行に当り、日本原子力研究所の方々には大変お世話になっております。記して感謝いたします。